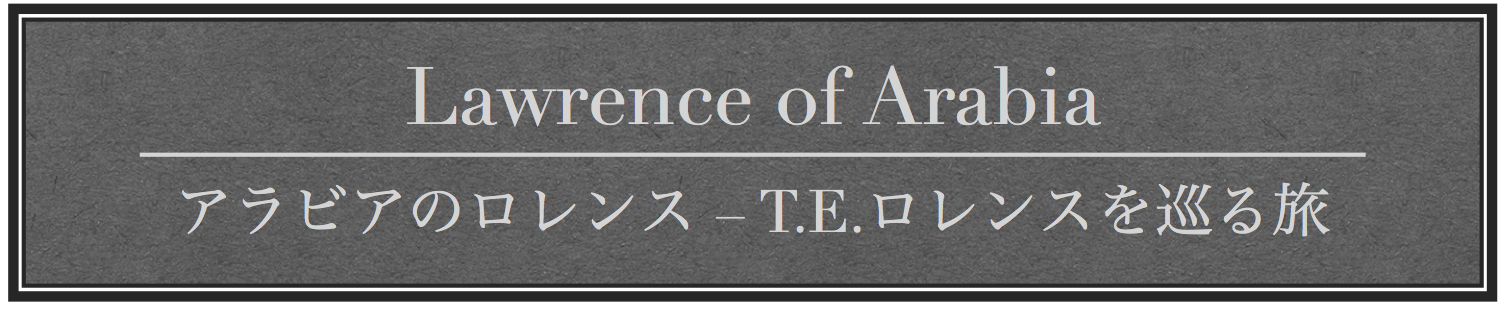アラビアのロレンス 回顧展 & 足跡を巡る旅 in UK Feb/2006
"Lawrence of Arabia : the life, the legend" at Imperial War Museum London / part 4
アラブの反乱
ー1916年のロレンスの手紙
1916年、ジェッダを訪問したロレンスは、フセインの息子達と面会した。「反乱を成功させるには、熱狂を持続させるカリスマが必要」と考えた彼は、3番目の王子であるフェイサルにその資質を見いだした。 反乱への援助を約束したロレンスは、フェイサルの軍事参謀として再びアラブの地に戻った(が、実際は戻るよう命令されると、自分は責任を負う仕事はイヤだし、性格的に現場なんて無理だと目一杯抵抗したあげくに、渋々アラブの地に戻ってます(笑)こんなエピソードは映画では描けないよね。) フェイサルからプレゼントされた純白のアラブ服に着替えたロレンスは、アラブ軍の中に入っていった。

アラブでのロレンス
回顧展ポストカードから拝借
しかし状況は酷かった。英国は、トルコと戦うためにアラブ軍の協力を必要としながら、「アラブの独立」を望まず、時代遅れの武器ばかり送ってきていた。戦闘員も、軍事訓練されていない寄せ集めのベドゥインたちだった。しかも、長年の因縁を持つ部族間の対立を調整しながらまとめていかなければならない(でもこれはカルケミシュで鍛えられたロレンスのお得意技)その中で彼が選んだのは、ゲリラ戦術だった。
彼は「軍隊」の形をもたないアラブ軍の短所を、むしろ長所と考えた。砂漠をものともしないベドゥインは、奇襲攻撃でこそ最高の能力を発揮する。そのため、必要な時にだけ部族を集めた、神出鬼没な行動を選んだ。さらにその戦術は、アラブ軍が攻撃を受けることも避られた。 そして、アラブ軍の人的被害を最小限に食い止めるため、直接的な戦闘よりも、相手を物質的に疲労させていく戦術を選んだ。それが彼に「エミール・ダイナマイト(ダイナマイト王)」のあだ名を与えた鉄道爆破だった。鉄道破壊はトルコ軍の物資にダメージを与え、さらにトルコの戦力がアラブ各地で足止めされるため、狙った街への襲撃を容易にした。そして列車爆破は、アラブ軍に戦利品も与えた(ロレンスはゲリラ戦を初めて「戦術」として理論化させたので、「ゲリラ戦術の父」とも呼ばれている。)
そして次にロレンスが狙ったのは、紅海に面した街アカバだった。この港町を奪えば、英国軍が北上するための足がかりとなり、またアラブ軍への物資補給も容易となった。しかし前方を海、後方に広大なネフド砂漠を持つアカバは難攻不落と言われていた。
だが、ロレンスは50人のベドゥインと共に、2ヶ月かけて横断不可能と言われたネフド砂漠を渡り、アカバを攻め落とした。この華々しい成果によってロレンスは少佐となり、またアラブ軍は英国の正規の戦力として認められるようになった。
さらに、このネフド横断で、ロレンスはべドゥインと共にラクダの肉を食べ、腐敗した水を飲み、時にはベドゥイン以上の強靭な体力を見せ、彼らに認められる存在となっていった。
長いですか?一番の山場だから許してね。
ある日、行動を共にしていた部族長が突きつけた一枚の紙に、ロレンスに衝撃を受けた。それは「サイクス・ピコ協定」と呼ばれる、英国とフランスによる戦後のアラブの分割統治案だった。アラブに独立を約束しながら、一方でフランスと植民地案をとりきめる英国の二枚舌外交に、ロレンスは苦悩する。
ー1917年の手紙
しかしロレンスは、「負けて約束を守るより、勝って約束を破る」道を選んだ。フェイサルにも、英国にも、全ての事実は語れなかった。そして英国という「国」ではなく、彼という「人間」を信頼するベドゥインたちが死んで行く中で、自らの欺瞞に対してロレンスの精神は崩壊寸前になっていた。
戦闘のたびに体に傷をうけ、目の前に転がるトルコ兵たちの死体に「早く悪夢から目覚めたい」と願った。しかし、村人全員を虐殺したトルコ軍の残虐行為を目の当たりにし、その軍隊の皆殺しを命じた。そして、自分を慕っていた召使いの少年が、戦闘で致命傷を負った時には、自らの手で殺した。ロレンスの手は血に染まっていた。
不眠不休の中で、ロレンスの体重は37キロにまで落ち込み、精神的にも肉体的にも限界にきていた彼の最後の望みは、シリアの首都ダマスカスをアラブ軍の手で奪還し、アラブ政府という既成事実を作り上げ英国に認めさせることだった。
そして1918年10月、ついにアラブ軍とロレンスは、解放の歓喜に湧くダマスカスに入城した。休むこともなくロレンスは市の行政機能を回復させ、フェイサルを呼び寄せてアラブ国民議会を立ち上げた。わずか3日の滞在でこれらをやり遂げたロレンスは、2年間戦ったアラブから逃げるように去った。
ー1918年の手紙

ダマスカスでのロレンス
回顧展ポストカードから拝借
通路を抜けた先にあった部屋は、まさに「アラビアのロレンス」の世界でした。
彼が撮影したジェッダの写真が大きく飾られ、こちらも「よしっ!ジェッダ上陸!」なんて気分(笑)そして、フェイサルにもらった絹のアラブ服やエンフィールド銃、腰につける短刀などが展示されていて、それだけでも単純に興奮してきちゃう。
壁一面に飾られた、ロレンスやフェイサル、部族長アウダたちの写真を見みながら音声ガイドに耳を傾けると、それは初めてのロレンスとフェイサルの会談のシーンでした。
「『この地、ワディ・サフラはいかがですか?』とフェイサルが聞いた。私は答えた。『良いところです。でもダマスカスからは遠いですね。』私の言葉は皆の間に剣のように振り落とされた。」
なんて、ロレンスの「知恵の七柱」からの朗読で、気分はすっかり「アラビアのロレンス」の中。
そして、この部屋には沢山の手紙や資料、ロレンスが爆破したヘジャーズ鉄道の部品、トルコ軍の資料などがありました。「ロレンスをカイロに呼び戻さないでくれ」と英国軍に頼むフェイサルの電報や、ロレンスにすぐに戻ってきて欲しいと書いた手紙などがあって(アラブ人とイギリス人の間の手紙なのに、フランス語で書かれてる(笑))フェイサルのロレンスへの信頼を感じました。
そこで笑ったのが「お買い物リスト」!!ロレンス達が奪還したアカバは物資が不足しており、その調達のため、ロレンスはすぐにラクダでシナイ半島を横断してカイロに向かいましたが、そんなシビアな場面での調達リストを「ショッピング・リスト」なんてネーミングはないだろぉ〜なんて思っていたら・・・うわぁ!本当に「ソックス:2足」とか書いてある(笑)
「ライフル:2000丁」とか「タバコ:6000本」なんてのは、「物資調達」って感じですが、「お茶:紅茶と緑茶」だの「ティーポット」だの・・・アフタヌーン・ティーでもする気かっ?!

そんな部屋で、目立たない壁の狭間の奥に、小さなアクリルの箱があり、その中には小さなダイアリーが置かれていました。ロレンスが携帯していたこの1917年のダイアリーは、「デラア事件」のあった日のページだけがなくなっていると解説されていました。
トルコ支配下の街デラアに侵入したロレンスは、トルコ軍に捕まり、ロレンス自身の言葉によると、トルコの軍政官に肉体関係を迫られ、拒否したロレンスはひどいむち打ちを受けた上に強姦されたといいます。これをロレンスの作り話だと考える研究者もいますが、「その日以来、私の中の一部が死んでしまった」とロレンスは語り、「たった5分間、苦痛から逃れるためにとりかえしのつかない過ちを犯した」と、自らを「汚れた者」と責め、生涯にわたり苦しみ続けました。
ページが欠けたダイアリーは、まるでロレンスの奥底の死んでしまった一部を見ているようでした。
しかも音声ガイドを聞くと、「知恵の七柱」のデラアの場面が・・・。重い気分で聴いていると、隣で小学生の子供がこの朗読を真剣に聞いている??!!ちょっとマズイだろ!!この音声ガイドにチャイルド・ロック機能はないのかっ!?
他には、ロレンスが後にジェッダで購入した巨大な木製の扉がありました。青銅のラインと細かい彫刻が美しいアラビア風の扉ですが、とにかく巨大!「こんなモンをよくイギリスまで持ち帰ったなぁ」と、ちょっと感心しちゃいました。これは、(後日訪れる)ロレンスのコテージ「クラウズ・ヒル」にあったそうですが、イギリスの田舎に、こんなに巨大で異国情緒たっぷりな物体がドカンとあったら、ご近所ビックリだよなぁ。
それからロレンスが、メッカで作った特注の短剣がありました。細かい金細工が本当に美しいんですが、大きさが普通の半分くらいしかないんです。普通の大きさでは扱いにくいからと、ロレンスが注文したそうですが、身長だけでなく、手も小さかったのか?
そして、ちょっと笑ったのは、ロールスロイスに乗ったロレンスが、ダマスカスに入城する有名な写真。他の写真は、大抵、美術館や博物館が管理しているのに、この写真の版権はちゃっかりロールスロイス社でした。
そして1918年のダイアリー。ロレンスは自分が捕まった時を考えて、記録というものをほとんど残さなかったそうで、これも(先ほどの1917年のも)その日にどこにいたのかだけが記入されていました。そしてここにはたった3日だけ「ダマスカス」と書かれていました。
そのダマスカスでのロレンスを描いた肖像画が掛けられていましたが、ロレンス自身も「後で見た時にショックを受けた」というほど、頭布のすきまからのぞくロレンスの顔はやせこけていました。
「知恵の七柱」でダマスカスでのシーンを読んだ時、歓喜で彼の名を叫ぶ群衆と、解放を祝うモスクからの祈りの呼びかけの声の中で、彼だけがこの解放がむなしく無意味だと感じていて、その空虚感にショックを受けました。一番喜んで欲しかったダフームはこの世におらず、そしてこの結末を分かっていながら、ここまで心身を消耗したロレンスを目の当たりにして、この2年間の残酷さをまじまじと感じました。